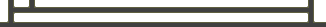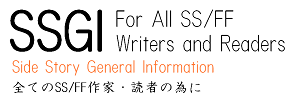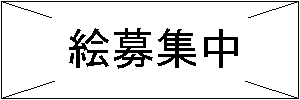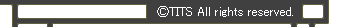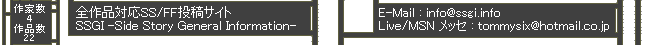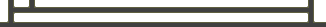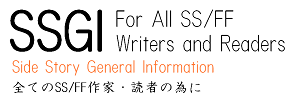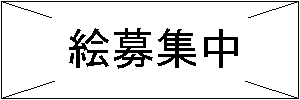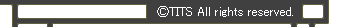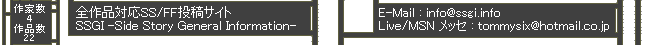|
二人の時間――長門有希の場合――
|
今日も今日とてSOS団へ出勤する。
なぜ行くかって?朝比奈さんを見るために決まってるだろう。
それ以外に何がある。……決してハルヒと一緒に帰るためじゃないぞ。
ちなみに今日俺は一人だ。といってもいつもハルヒと一緒にいるわけじゃないんだがな。
そんなことを考えているうちにいつもの扉の前に立っていた。習慣でノックする。
「………どうぞ。」
ん?この声は…
ノブを回して部屋に入る。
「なんだ、長門だけか?」
古泉はおろか、部室専用のエンジェル。朝比奈さんまでいなかった
「少し話がある。」
普通の人にはわからんかも知れんが、どことなく悲しげな表情の長門だった。
なれたな、俺も。
「座って。」
そう言って、いつもの位置から古泉の席、つまり俺の正面に座った
「どうしたんだ?長門が話なんて……またなんかあったのか。」
長門は、少し黙った後こういった。
「キョン君、私あなたのことが好きです。」
長門が俺のことをキョン君と呼んだことにも驚いたが、その後の一言に俺は度肝を抜かれた。
なんだって?
「好き。あなたのことが。」
いつもの長門か?しかし目には少し涙がたまっているように見える俺は眼科に行ってきたほうがいいのだろうか。
「すまん、さっきみたいに言ってくれるか。」
「私はあなたが、キョン君のことが好きです。大好きです。」
これはかなり大変なことだぞ。長門は確かに無口だが美人であり、隠れファンも多いらしい。(谷口談)
つまりこんな場面をファンの人に見られればフルボッコ確実だ。
…さて、なんと答えるべきか。…まぁ、長門なら知っているかもしれない。話してもいいんじゃないだろうかな。
「あのな、長門。俺は「わかっている。」
やっぱりな
「あなたは涼宮ハルヒが好き。わかっている。」
無駄かも知れんが聞いておこう。いつから知っていた
「あなたは涼宮ハルヒの近くにいるときにだけ見せる特別な顔がある。そのことを朝比奈みくるに質疑したところそのような応答を得た。」
なるほどね
「ちなみに古泉一樹も知っていると思われる。」
……あぁ〜、誰か拳銃を持ってないか。あのにやけ面を消し去るためには奴の脳天を打ち抜く必要があるようだ。
「そこであなたに対して私からの希望がある。」
何でも言ってみろ。お前には世話になっているから可能な限りかなえてやろう
「――――がほしい。」
「え?」
よく聞き取ることができなかった。いつもよりさらに小声だった。
「あなたの余った時間がほしい。」
えーと。どういう意味なんだろうか。
「少しでいい。あなたの余った時間がほしい。」
驚いたことに長門は泣いていた。大粒の涙をこぼしてらっしゃる。
ということはさっきのも見間違いじゃないんだろうな
…俺のせいか?!
「私は本当にあなたのことが好き。でも、この気持ちがあなたに届くことはないと思っている。…涼宮ハルヒもそれを望んでいる。
そしてあなたの心も涼宮ハルヒからは動かないと思ってる。…でも、あなたにあまっているわずかな時間がほしい。私にそれを使わせてくれるその許可を……」
お願い。と、小さくつぶやいた長門はこちらをじっと見ている。あの液体ヘリウムみたいな目が、絶対に見せないと思っていた涙を流しながら。
……俺はどうすればいいんだろう。確かに俺の気持ちはハルヒから動くことはないだろう。あの団長様を愛してしまっているんだから。
…でも、長門は俺を求めている。あの絶対になかないはずの宇宙人製人造人間。長門有希が泣いているのだ。どれだけ辛かったんだろう。
俺とハルヒが近くにいるたびに心がいたんじゃないだろうか。俺も、ハルヒが古泉の近くにいると同じ気持ちになってしまうからこの気持ちはいたいほどわかる。
俺は、立ち上がって長門の後ろに回りこみ、優しく長門を抱きしめた。俺ができる限りやさしく包み込むように抱きしめた。
「……な……に??」
「何も言うな。…長門。この短い時間だけだが、お前にこの時間を使っていいことにする。…すまなかったな、何も気づけなくて。」
……長門は、少し躊躇した後に、弱弱しく俺の体に手を回した。
しばらく抱き合った後、俺達は重なり合った。こんなにやわらかいんだな。唇って。
二度目のキスだったが改めてそう思った。
そして長門は、終始声を上げずに泣き続けていた。それがうれし涙なのか一緒になれないことを悲しんでいる涙なのかはわからない。
でも…長門が少しでも気持ちを晴らすことができたなら。
涙を流すほどの気持ちを少しでもやわらげることができたのなら、それでいいのではないかと思う。
「長門。」
「なに?。」
「本当に、すまなかったな。」
少し黙った後長門は少し首を横に振って
「……いい。」
つぶやいた。
長門は、泣き腫らして真っ赤になった目でこちらを見上げ、少しあのときのように少し笑った表情でこう言った。
「こうして、一緒にいることができるだけで……いい。」
それから俺と長門は、ハルヒが100Wの笑顔で飛び込んでくる寸前まで、ずっと並んで手をつないでいた。
|
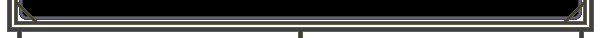
|
|